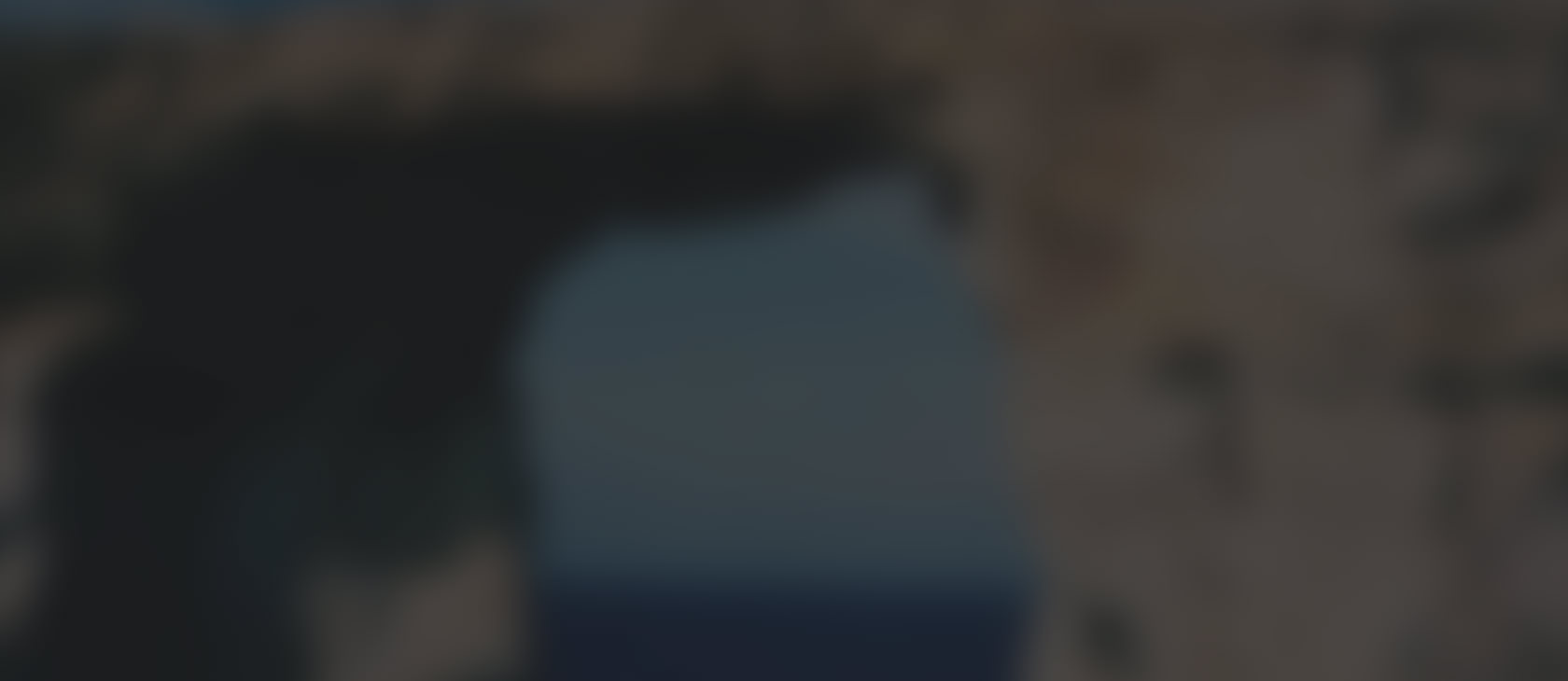ゲームによるストーリーの消費
きょうは森上さんがON THE TRIPにたどり着くまでの物語を聞かせてほしいと思っています。森上さんはエンジニアであり、UI/UXデザイナー。でも、そのどちらでもない気もしています。そのルーツには、ゲーム三昧だったという高校時代がありますよね。
森上:当時はゲームをするために生きてましたね。両親が家にいないことが多くて、基本的に起きてから寝るまでずっと一人の生活だったんですよ。なんで、きょうは学校に行くのダルいな~と思ったときに、ぼくのケツを叩いて「いけ!」と言う人がいなかった。それで、そのままサボってゲームしてたんです。それがまかり通ってしまったのが、その後の社会不適合なぼくを生んだ原因ですね。
オンラインゲームですか?
森上:そうですね。一人っ子なので、家でゲームをやるときも一人じゃないですか。だから、FFやドラクエみたいなRPGなら一人で遊べるので、ずーっとやってたんです。でも、やり尽くしちゃったんですよ。やりすぎて。そうなると、「もっとおもしろいものを」って探しはじめるじゃないですか。そのときに知ったんです。オンラインゲームというのがあるらしいと。

森上:中学生のころ、電話回線から専用のネット回線になりました。定額でインターネットができる時代になると、オンラインゲームがどんどん出てくるようになって。その波に乗ってしまったんですね。大学に入ってからも、ひたすらゲーム。ただ、最後のほうはゲームをやるっていうよりは、漫画や映画の消費と近い感覚で「ストーリーの消費」をしていました。もっと新しいコンテンツに触れたい、みたいな。
ぼくも重度のアニメ好きですが、名作を片っぱしから消費していく時期がありました。古典を学びつつ、現代の作品までコンプリートしていくような感覚ですかね。
森上:で、おもしろい、おもしろくないって言いあうわけです。当時、オンラインゲームのようにみんなでわちゃわちゃ遊べるというのはインターネット上にしかなかったんです。ぼくは「みんなで飲み会いこーぜ!ウェーイ!」というような学生ではなかったですが、ずっとひとりで過ごすのもそれはそれで寂しい。だから、仲がいい友だちを巻き込んで、オンラインゲームで顔も知らない人たちと何十人で遊ぶということをやってましたね。
エンジニアでありデザイナーであり経営者
ゲームが好きで、ゲームを作りたくてエンジニアになった、というわけではないのですか?
森上:それが、そうでもないんですよ。大学1年目は腐れニートみたいな生活をおくってたんですが、2年生になるときにスイッチがはいって。意識高い系大学生にジョブチェンジしたんですよ(笑)。そこからは暗黒期なんですけど。
え、そこからが黒歴史なんですか?
森上:正直、ネトゲ廃人だったときよりも恥ずかしいです。ビジコンを主宰する団体の代表になって活動をはじめたんです。企業から協賛を頂いて、ビジネスコンテストを開いて、審査員として社長さんをお呼びだてして、予選と本戦をやって、というような。ビジネスとはなんぞやと、ビジネスもやったことないのに分かった気になってやってたんですけど。
大学生でそこまでやっていたら、かっこいいじゃないですか。
森上:いやあ、もう意識高い系の勘違い系ですよ。実際にビジネスを立てるのとは、ものすごい差がありますから。あれで分かった気になってたのが恥ずかしいなぁという。しかも「日本を元気にする!」とか言う団体がたくさん出て来た時代だったので(笑)。あるとき、冷めちゃったのか、疲れちゃったのか、「なんかこれは違うぞ」と思ったんですね。元気にするってどこの立場から言ってんだろう?とか、そもそも日本って元気ないんだっけ?とか、違和感を感じるようになって。

森上:でもこの道に進むきっかけになったのは黒歴史時代の話で、イベントをやるには集客をしなくてはいけない。そのときに、ポスターを作りはじめたのがデザイナーとしての原体験。デジタルではなく、紙でした。それからどハマりして。広告とかキャッチコピーとかプロモーションとか、マーケティング施策とか、行動変容をいかに起こすかという本質的なところが面白くて。紙からネットに推移していく時代でもあったんで、その流れでホームページも作れるようになろうとHTMLを書きはじめたのが大学4年。これにまたどハマりして。コーディングは今でも苦手は苦手なんですけどね。
どハマりする集中力がやばいですよね。メンバーで石垣島に行ったときも、森上さんは徹夜でひたすらコードをいじってました。ぼくが寝たときに見た姿と、起きたときに見た姿、そのフォームが寸分たりとも違っていないことに戦慄を覚えましたよ。
森上:そうっすかね(笑)。それで、大学4年のときにシェアハウスもはじめたんです。当時ぼくよりコーディングができるやつと、カメラマンと、デザイナーのぼく。3人で暮らしながら、3人でウェブ制作の仕事を受けたりしてたんです。そうこうしてるうちに「アイドルをつくりたい」と言い出すやつが現れて。面白い子だったので、その立ち上げを一緒にやりました。オーディションをしてメンバーを決めて、ウェブサイトをつくって、ポスター含めて告知して、今までやってきたことを全部詰め込んだ大学時代の集大成になりました。今はメジャーにいっちゃってるので、グループの名前は出せないんですけど、すごく面白かったなーと。
起業、そしてミューロンを経て
就活はしなかったんですか?
森上:起業しようと思いながらも、やっぱり勇気がなくてなかなか踏ん切りがつかなかったんですが、とある企業が、新卒チームの事業を完全子会社化して会社を起こさせようというプロジェクトをやってたんです。社内でビジコンをやって優勝したチームが法人化できるという。で、ぼくたちのチームが優勝して会社を立ち上げさせてもらって。それから8本ぐらいアプリを作ったんですが鳴かず飛ばずで。結局、僕の家庭の事情もあって会社をたたませていただくことにしました。そのタイミングで最初フリーランスとして「ミューロン」という会社に加わることになったんです。ただ、ぼくと入れ違いでミューロンにいたエンジニアがいなくなってしまって。ぼくの手元に残ったのは、見たこともないバックエンドのコードと、触ったことがないハイブリッドのアプリケーションのコード。ぼくしかいないんで、ぼくがやるしかない。それが3年前。でも、分からないなりに書いているうちに分かってくる。ミューロンは1対1でダイエットをサポートするようなサービスで、昔は実際にトレーナーとユーザーさんが1対1でチャットをしていたんです。そこで、ユーザーさんが送ってくるメッセージを簡単に解析して、なんて返したらいいかという候補を出して、選択して編集するだけで返信できるというシステムをつくったりしていました。
それって、技術的にもかなり高難度な領域ですよね。短期間でどうやってそこまで成長したんですか?
森上:それ以外のことをなんも考えてなかったからですかね。1年目は寝るか、書くかの生活。2年目にはデザイナーが抜けることになったので、昔デザインをやっていたのもあってぼくがデザイン領域も見るようになって。コードを書いてデザインもするようになったのは、これがきっかけです。開発メンバーが入る前はさらにてんわやんわになって、ヒアリングをして、画面のラフをつくって、検証して、アニメーションを考えて、表も裏も実装して、リリースもやる。いま考えるとよくあんなことができたなぁと思うんですけど、始めた同時と比べるとこの3年で技術力はだいぶマシになりました。
ぼくにとって森上さんはスーパーエンジニアなんですよね。「ちょっとここをこうしたい」って、紙のデザインを修正するような感覚で相談しちゃうんですけど、それがアプリであろうとウェブサイトであろうと、パパパってなんでも実現しちゃう。

どうなりたいか、どう生きたいか
そんな森上さんが ON THE TRIP を立ち上げた理由はなんですか?
森上:ぼくは自分の仕事において「文化になるサービスをつくる」という理念があって。もう4,5年も前の話になりますが、好きなグラフィックデザイナーが「求められているのは『どうなりたいか、どう生きたいか』という価値観を思い出させてくれるものだ」って言ってたんです。iPhoneもMacもアップルの哲学に触れることで、自分の価値観を思い出させてくれる、みたいな話です。「文化になるサービスをつくる」という考えは、それと密接にひもづいてるんですけど、「どうなりたいか、どう生きたいか」を思い出させてくれるプロダクトには独特の空気感が必ずありますよね。あれって一瞬の「文化のかたまり」だと思うんです。アップルやスタバがそういう文化を提供しているのだとすれば、ああいう文化になるサービスをつくりたいと考えていました。そのとき、ON THE TRIPのラフにあった「そして、アートはあなたに問いかける」という言葉を見たんです。

森上:そのとき、自分の価値観を思い出させてくれるものって、答えじゃなくて「問いかけ」のほうだなと気づいたんです。アップルもスタバも自分たちが信じているものを見せている。でも、それはユーザーにとっての「答え」を見せてるわけじゃない。信じているものを通して、それに対して「あなたがどう感じるか」と問いかけているんだと感じて。同時に、物語というのも問いかけだな、と。コンテンツを消費しまくってきた人間として思っていることですが、ゲームとか映画とかアニメとか小説とか、コンテンツを見て「やばい!」と人の心を打つ瞬間って、その物語が根幹で発している「問いかけ」が、受け手の価値観を掘り起こしたときだと思うんですよ。
ON THE TRIPの根幹にある価値は「物語」。それは「問いかけ」であり、価値観を思い出させてくれるサービスというのは、まさにこういうことなのかもしれないと思いました。旅先にある物語にあらためて向き合う中で「どうなりたいか、どう生きたいか」を問いかける。そして、自分の価値観を思い出す。これはすげえ話だなと。トラベルガイドなんですけど、もはやそういう次元じゃない。これが本当にうまく届けば、熱狂する人が生まれるサービスになるんじゃないかと思ったんです。
透明感のあるデザインで物語を届ける
森上さんは ON THE TRIP で、どんな物語をつくっていこうと思っているのですか?
森上:ぼくは物語を届ける役割かなと思っています。ON THE TRIP のガイドは物語であり、どちらかといえばアートに近い。今は今でかっこよさに振り切れていて心踊るんですが、本当はアプリのデザインやシステムもアートにしてしまっては、ごちゃごちゃになってしまいます。むしろぼくはその物語をどこまで深く響かせられるかということを考えていきたい。
ぼくは今のUIも読みやすいというか没入できる感じになっていると思うんですけど、それがさらにどうなっていく構想があるのですか?
森上:もっと「透明感」のあるデザインにしていきたいと考えています。ぼくが思う「透明感」とはこういうこと。デザインって、そこにデザインがあるって思われたら終了で、それっていいデザインじゃないと思うんです。技術もまた然りで、グーグルの検索がそうですけど、あれってものすごいテクノロジーのかたまりですが、ユーザーは一切そんなことを感じない。あそこまでいくと「文化をつくった」と言える領域だとぼくは思っていて。そういう意味で、今のアプリはまだ設計が甘いところがあって、画面の操作で迷ってしまったり通信環境で体験が途切れたり、物語を深くまで響かせたいと思ったときに壁があって。実装しといてなんですが、ページめくりのエフェクトもはずしたいぐらいなんです。「うぃん」ってなるのは気持ちいいんですけど、「うぃん」ってなることで、物語の質量を殺している。あれはデザインがあることを感じさせる演出なので、ぼくとしては透明度が高くない。

森上:デザインはユーザーとぼくらのあいだにある壁だと思っています。これが不透明であるほど、ぼくらの伝えたいことは届かないし、透明であるほどユーザーにスパッと届くと思うので、このフィルターが邪魔をしてはいけないと思うんです。これは技術に関しても同じことで、通信速度や通信回数を気にしなくても、ふつうに見れて、ふつうに聞けたほうがいい。ユーザーからすると「ふつう」なんですけど、それを実現するのってレベルが高い。そこをなんとか、技術を感じさせずに「ふつう」に使える状態に持っていくのがいい技術だと思っています。
リストからどのガイドを選んでも、すっと入って、すっと音声が流れますが、そういう「ふつう」が難しいことなんですね。これをもっと自然に使えるよう磨いていく、と。
森上:突き詰めていくと、「伝えたいことを伝える」「届けたい価値を届ける」というのが媒体の役割。それはウェブだろうとアプリだろうと本質的なところは同じです。そのとき、果たして黒背景がいいのか、白背景がいいのか、ページめくりのエフェクトは必要なのか、と考えていく。ただ、その段階はもう少し先かなとも思っています。いちばん最初にそこまでいけるといいんですが、最初に触ったときって、目新しさとか人に言いたくなるところが多ければ多いほどいい。ちょっとこってりしてるぐらいのほうが、ひとくち目はいいのかなとも思います。
今のアプリのUIは旅のはじまりにすぎない、と。
森上:コモディティ化するほど、薄味になっていくのかな。iPhoneのアイコンのデザインも最初は現物にのっとってデザインしていました。あれはタッチパネルが世の中に普及していなくて、人間が画面の中でどれを触れてどれが触れないのか、判別できなかったから。だから、なるべく現物に近い立体的なアイコンにして、こってりしたデザインになってたんです。でも、みんながタッチパネルに慣れた結果、別にこってりさせなくても、どこを押せばいいのかが分かるようになった。そこで、もういらないよねとフラットな薄味になっていった。基本的に「現物にのっとったこってりしたパーツ」が画面に多ければ多いほど、人間の脳はその情報の処理に労力を要する。微細な違いや陰影から「そのパーツが何であるか」を判断しなくちゃいけませんから。慣れたら簡単に判断できる範囲でなるべくシンボル化させて、パーツあたりの情報を少なくしていくのが人間にとって優しいんです。
ON THE TRIPは「エンジニア」を募集しています
ぼくたちは、森上さんが話してくれたような未来をともに作ってくれる仲間を募集しています。森上さんは、どんな仲間がほしいですか?
森上:開発陣が担うのって、「より多くの物語や問いかけが、より多くのユーザーに、より響くように」というところだと思うので、ユーザー寄りの人と働きたいです。デザイン力や技術力が高くてもそういうところにロマンがないとか、ユーザーに興味がないとかは、あんまり合わないというか、あまり一緒に働きたくないなーと思います。あとは「エモいとキモいの狭間にいる人」というのも必須になると思います。弊社のメンバーはみんな紙一重なので(笑)。
興味があれば、ぜひ上記の応募フォームからご連絡ください。
READIO ON THE TRIP vol.4。エンジニア兼デザイナーでもある森上さんにお話を聞かせてもらいました。